経絡の流注
- Shyuichi Nakamura

- Apr 14, 2022
- 2 min read
関節に注目している人は、経絡という言葉を聞いただけで敬遠してしまう人がいるかもしれません。
内科と整形外科みたいな違いがあると思っている人も多いのではないかと思いますが、それは大きな誤解です。
部分的に焦点を当てれば、全く別物に思えるかもわかりませんが、同じ人間の身体ですから決して別物ではありません。
鍼灸も経絡やツボを使って治療をしますので、経絡やツボだけみた景色というのも片寄って見えます。
動きがない経絡の解釈は、どうしても落ち度がありますので、様々な角度から見ていく必要があります。
経絡には流注というのがあって、各経絡が体表面を流れ、体内にも入り込み、各臓腑とつながっていると書かれています。流注を学んでみると非常に面白いことがわかります。
この前から上部頸椎の血管やその前側にある咽の話しを書いてみましたが、十二ある経絡の殆どは咽や肺と関わっているようです。
また肺経は、十二ある経絡の一番最初にでてくる経絡です。そして風邪は万病の元と昔から言われるように、咽や肺は、病気の入り口だと考えられています。
流注が肺や咽を通る経絡が多いのは、このことに古人達が気づいていたからではないかと思います。昔から感染症は、病の根本だということをわかっていて治療をしていた訳です。決して今と全く違うアプローチをしている訳ではないということです。
だからこそ、咽や肺の問題は、注意深く観察していく必要があります。そして咽の奥にある環椎後頭関節の動きを調整すると、原因不明の症状を改善させるのに役立つことが多いのではないかと思います。
いわゆる器質的疾患は、西洋医学的なアプローチが必要な場合もありますが、肺系統へのアプローチというのは最も重要なものだということです。
抵抗力をあげるとか、免疫力をあげると言っても、咽や鼻、肺がしっかりしていないとうまくいかないということが多いということです。
そして、肺や咽、鼻は、非常に変化の早い部位です。状態が良くなってもちょっとしたことですぐに悪くなってしまったりします。常にチェックしている必要があります。
自然治癒力というのは、肺系統がしっかりしてこそ成り立つのだと思います。

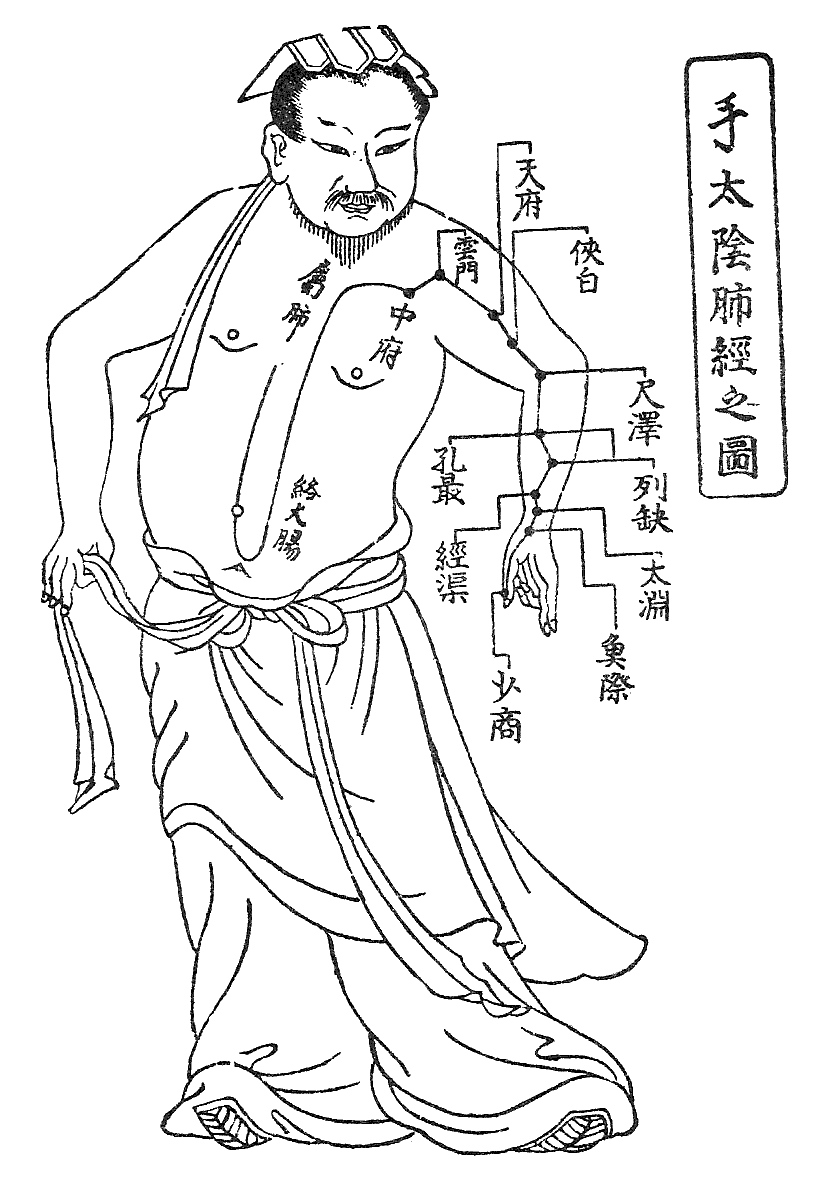













Comments